「肺胞蛋白症」とはどんな病気?

肺胞蛋白症は、肺の奥にある「肺胞」と呼ばれる小さな空間に、必要以上の蛋白質がたまってしまう、まれな病気です。
蛋白質がたまりすぎると、肺の大切な役割である「酸素を取り込んで二酸化炭素を出す」という働きがうまくいかなくなり、その結果、息苦しさなどの症状が現れることがあります。
この記事では、肺胞蛋白症の特徴や症状、診断の方法、治療法についてご説明いたします。
1. 特徴
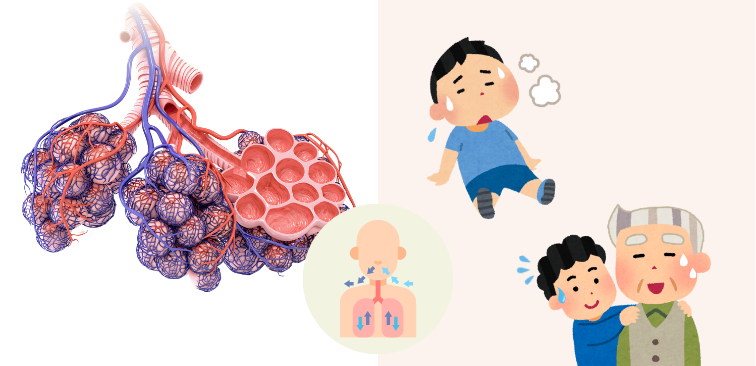
肺胞蛋白症は、肺の正常な働きを助ける「サーファクタント」という物質が、うまく処理されずに肺の奥深くで蓄積してしまうことで起こる病気です。
サーファクタントは、肺胞という小さな袋の表面にある物質で、肺胞の表面張力を減らして呼吸を楽にしてくれる大切な役割を持っています。
通常、肺胞内の「マクロファージ」という細胞が、古くなったサーファクタントを片付ける役目を担っています。
しかし、肺胞蛋白症では、この片付ける機能がうまく働かず、サーファクタントがどんどんたまってしまい、肺が酸素と二酸化炭素の交換をスムーズに行えなくなります。その結果、息苦しさなどの症状が現れるのです。
肺胞蛋白症には、主に3つのタイプがあります。それぞれのタイプによって原因が異なります。ここからは、それぞれの特徴についてご説明いたします。
【自己免疫性肺胞蛋白症】
肺胞蛋白症のなかで最も一般的なタイプで、全体の約90%を占めています。このタイプでは、からだの免疫システムが誤作動を起こし、本来は肺の中でサーファクタントを処理するために必要な「GM-CSF」という物質を攻撃してしまうことが原因です。
GM-CSFは、肺胞内で古くなったサーファクタントを処理する「肺胞マクロファージ」という細胞の成熟や働きをサポートする重要な役割を持っています。
しかし、自己免疫性肺胞蛋白症では、免疫がこのGM-CSFを異物と見なして攻撃するため、マクロファージが十分に機能できなくなり、サーファクタントが肺に蓄積してしまうのです。その結果、呼吸が苦しくなるなどの症状が現れます。
【続発性肺胞蛋白症】
ほかの疾患や環境要因が原因で発症するタイプで、背景にさまざまな原因が関わっています。たとえば、血液の病気や免疫異常がある場合や、粉塵(例えば、工業で使われる特定の物質)を吸入したことがきっかけで発症することがあります。
続発性肺胞蛋白症の場合、原因となる疾患や環境要因を特定して対処することが、症状改善への第一歩になります。
【遺伝性肺胞蛋白症】
非常にまれなタイプで、遺伝子の異常によって発症します。とくにお子さまに多く見られるのが特徴です。
遺伝的な問題であるため、同じ家族内で発症するケースがあります。遺伝性肺胞蛋白症は根本的な治療が難しい場合もありますが、早期の診断により、症状を管理するためのサポートが可能です。
肺胞蛋白症は、発症年齢に幅があり、40歳前後の方に比較的多く見られる一方、お子さまから高齢の方まで、どの年齢でも発症する可能性がある病気です。また、女性よりも男性が発症しやすい傾向が見られます。
発症頻度は非常にまれで、約10万人に1人とされています。そのため、一般的にはあまり知られていない病気ですが、適切な診断と治療を受けることで、多くの患者さんが症状の改善を経験しています。
【参照文献】日本呼吸学会肺胞蛋白症診療ガイドライン 2022 作成委員会 『肺胞蛋白症診療ガイドライン202』
https://www.jrs.or.jp/publication/file/pap2022_241009.pdf
【参考情報】Mayo Clinic “Pulmonary Alveolar Proteinosis”
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17398-pulmonary-alveolar-proteinosis
2. 症状

肺胞蛋白症の症状は、病気の進行状況によって現れ方が異なります。初期にはほとんど症状がないこともありますが、進行に伴い、次第に以下のような症状が目立つようになります。
【主な症状】
・息切れ:肺胞蛋白症で最も一般的な症状であり、とくに運動時や階段を上るときに感じやすくなります。全国調査によると、患者の約39%に労作時の呼吸困難が見られます。
初期には軽度の息切れですが、時間とともに進行することが多く、日常生活に影響を及ぼすほどの呼吸困難に至る場合もあります。
・乾いた咳:痰を伴わない乾いた咳が続くことがあり、ときには何週間も続くことがあります。調査によると、乾いた咳だけが症状の約10%の患者さんに見られます。
・喀痰(たん):まれに咳とともに痰が出ることもあります。
・体重減少:呼吸が苦しくなり、食欲が低下することで体重が減少することがあります。
・発熱:肺の感染症を併発した場合に、発熱が見られることがあります。
・全身倦怠感:からだが酸素を十分に取り込めないため、全身の疲労感を感じやすく、日常的に強い疲労感が生じることも少なくありません。
・胸痛:まれに胸の痛みを伴う場合もあります。
肺胞蛋白症の症状は、全国調査によると、約31%の患者さんが無症状で、健康診断やほかの検査中に偶然に発見されるケースが少なくありません。
これらの症状は徐々に進行することが多く、最初は軽い息切れ程度だったものが、時間の経過とともに症状が悪化し、次第に日常生活に支障をきたすほどの呼吸困難へと進展する可能性があります。
症状が徐々に現れるため、「年齢のせい」「運動不足」と思ってしまい、受診が遅れることも少なくありません。
肺胞蛋白症では画像上では特徴的な所見が確認できるものの、実際の症状は比較的軽微であることが多く、検査結果と患者さんの症状が一致しない場合があります。
また、病型によっても症状の現れ方に違いがあり、自己免疫性肺胞蛋白症では上記のような典型的な症状が多い一方、続発性肺胞蛋白症の場合は基礎疾患に関連した症状も加わることがあります。とくに、先天性肺胞蛋白症は新生児期から重篤な呼吸不全を伴うことがあり、早期からの注意が必要です。
また、肺胞蛋白症は、蓄積したサーファクタントが細菌の増殖を促進するため、感染症にかかりやすくなる傾向があります。
とくに風邪のような症状が長引いたり、繰り返し肺炎を発症する場合には、肺胞蛋白症が関与している可能性も考えられます。
その他、通常の肺炎やウイルス感染症に加えて、真菌(カビ)や非結核性抗酸菌といった一般的には感染しにくい病原体に対しても感染しやすくなることが知られています。
このため、日常的な感染予防を心がけることが重要であり、とくに感染症状が長引く場合には早めの受診が推奨されます。
肺胞蛋白症の症状には個人差が大きく、軽度の息切れ程度で収まる方もいれば、進行して重度の呼吸不全に至る方もいます。
しかし、早期に適切な治療を受けることで、症状の改善や病気の進行抑制が期待できます。
そのため、息切れや咳が長期間続く場合には、ためらわずに医療機関を受診することが大切です。
とくに、呼吸が苦しくなる症状が続く場合には、肺胞蛋白症に限らずほかの呼吸器疾患の可能性も考えられるため、専門医による正確な診断を受けることを検討しましょう。
【参照文献】難病医学研究財団『肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性)(指定難病229)』
https://www.nanbyou.or.jp/entry/4774
3. 診断・検査

肺胞蛋白症の診断は、症状、身体所見、および複数の検査結果を総合して行われます。以下は、主な診断および検査方法の詳細です。
・問診と身体診察
医師が患者さんの症状、既往歴、生活環境について詳しく聞き取ります。また、聴診器で肺の音を確認し、呼吸の様子も観察します。
・胸部X線検査
肺の全体的な状態を確認するために行われます。肺胞蛋白症では、両側の肺にすりガラス状の陰影が見られることが多いです。
・胸部CT検査
X線より詳細に肺の状態を観察できる検査です。肺胞蛋白症の特徴として、「地図状のすりガラス影」や「メロンの皮」に例えられる舗石状の陰影が現れることが多いです。
・血液検査
血液中の酸素濃度や炎症の有無を確認します。肺胞蛋白症の疑いがある場合、KL-6、SP-D、SP-Aといった項目が上昇することがあり、特に自己免疫性肺胞蛋白症では、抗GM-CSF抗体という特殊な抗体が検出されることもあります。
・肺機能検査
肺活量や一酸化炭素拡散能などを測定し、肺の機能がどの程度低下しているかを評価します。
・気管支肺胞洗浄(BAL)
肺胞蛋白症の確定診断において重要な検査です。気管支鏡を使用して肺の一部に生理食塩水を注入し、回収した液体を分析します。肺胞蛋白症では、回収液が「米の研ぎ汁」に似た乳白色の外観を呈するのが特徴です。
・肺生検
まれに、確定診断のために肺の一部を採取し、病理医が顕微鏡で詳しく検討する肺生検が行われることもあります。
【肺胞蛋白症のタイプを特定する】
肺胞蛋白症の診断が確定したら、どのタイプの肺胞蛋白症かを特定するための検査を行います。
・自己免疫性肺胞蛋白症の診断
血液中のGM-CSF抗体濃度が基準値よりも高い場合、自己免疫性肺胞蛋白症と診断されます。GM-CSF抗体は自己免疫性肺胞蛋白症の診断に役立ちますが、診断確定後にタイプを分類するための検査であり、単独では診断に十分ではありません。
・続発性肺胞蛋白症の診断
GM-CSF抗体が低値で、血液疾患や粉塵吸入、感染症など肺胞蛋白症の原因となる背景がある場合には、続発性肺胞蛋白症と診断されます。
・遺伝性肺胞蛋白症の診断
上記に該当しない場合、遺伝的な要因が考えられ、遺伝子検査が必要です。
以上のように、患者さんの状態に応じて、これらの検査を組み合わせることで、肺胞蛋白症の診断精度が高まります。また、ほかの呼吸器疾患と区別するためにも重要です。
肺胞蛋白症は稀な疾患だと言え、一般の医療機関では診断が難しい場合もあり、呼吸器専門医のいる大きな医療機関を受診することが必要です。
なお、肺胞蛋白症は一般的に一生付き合っていく必要があり、厚生労働省の指定難病に該当しています。一定の基準(管理重症度III度以上)を満たせば、医療費の補助対象となる可能性があります。
ただし、必ずしも重い症状が現れるわけではなく、20〜30%の患者さんでは病状が自然に軽快する場合もあります。完治はしないものの、適切な管理を続けることで、直接的な死因となる可能性は比較的低いとされています。
症状が進行して酸素不足を感じる場合は、酸素吸入を始め、必要に応じて全肺洗浄を行うことも検討されます。
また、前述のとおり、細菌やウイルスからからだを守る役割を持っている、肺胞内のマクロファージの働きが低下するため、一般の方にはかかりにくい真菌や非結核性抗酸菌などの感染症にかかりやすくなることがあります。
まれに、一部の患者さんでは、原因不明で肺が硬くなる(間質性肺炎や肺線維症)症状が進行し、呼吸困難が悪化するケースもあります。
このため、上記のような定期的な血液検査やレントゲン、CT、肺機能検査を行い、酸素吸入や全肺洗浄の必要性、感染症や間質性肺炎の合併の有無を確認するようにします。
病状が一度改善した後に再度悪化するケースも多いため、定期的な経過観察が重要です。症状が軽くても、感染症や間質性肺炎が静かに進行し、症状が現れたときには病状が進んでいる場合もあります。
肺胞蛋白症は、症状が乏しいことが多い反面、病変が広がりやすいため油断できません。継続的な通院と定期検査が重要であり、定期的な受診が必要だといえるでしょう。
4. 治療

肺胞蛋白症の治療方法は、症状の重さや原因に応じて異なります。ここでは主な治療法についてご説明します。
1. 経過観察
症状が軽く、安定している場合は、定期的に検査を行いながら病状を観察することが一般的です。この間、患者さんご自身が禁煙や感染予防などの日常管理を行うことが重要です。
2. 全肺洗浄療法
最も一般的で、効果的であるとされている治療法です。全身麻酔をかけて、肺の中に大量の生理食塩水を注入し、蓄積したサーファクタントを洗い流します。通常、片方の肺ずつ別々の日に行われます。
全肺洗浄療法の手順
1. 全身麻酔をかけ、気管に挿管を行います。
2. 片方の肺に生理食塩水を注入し、もう片方の肺で呼吸を続けます。
3. 注入した生理食塩水を排出し、この手順を何度か繰り返します。
4. 排出される液体が透明になるまで洗浄を続けます。
この治療法により、多くの患者さんで症状の改善が見られます。ただし、効果の持続期間には個人差があり、数か月から数年後に再度治療が必要になることもあります。
3.GM-CSF療法
自己免疫性肺胞蛋白症の患者さんに対して行われる治療法です。GM-CSFを吸入または皮下注射で投与することで、肺胞マクロファージの機能を改善させます。
4.リツキシマブ療法
自己免疫性肺胞蛋白症の一部の患者さんに効果があるとされる治療法です。抗GM-CSF抗体を産生するB細胞を減少させることで、症状の改善を図ります。
5.肺移植
ほかの治療法が効果を示さない重症例において、最後の選択肢として考慮されます。ただし、肺移植は非常にからだに対する影響が大きい侵襲的な治療法であり、慎重に検討する必要があります。
6.対症療法
酸素療法:呼吸困難が強い場合、酸素吸入を行います。
感染症対策:肺炎などの感染症を併発した場合は、適切な抗生物質治療を行います。
【対症療法・・・病気によって引き起こされる症状を和らげたり、消したりするための治療法】
7.生活指導
禁煙:喫煙は肺の状態をさらに悪化させるため、必ず禁煙が必要です。
感染予防:手洗いやマスク着用など、日常的な感染予防策を徹底します。
運動:可能な範囲で適度な運動を行い、体力の維持に努めます。
治療法の選択は、患者さんの症状の程度、全身状態、生活環境などを考慮して、医師と相談しながら決定します。また、治療効果や副作用についても十分に説明を受け、理解したうえで治療を進めることが重要です。
肺胞蛋白症の治療は長期にわたることが多いため、医療チームとの信頼関係を築き、継続的な治療とフォローアップを受けることが大切です。
また、同じ病気を持つ方々との交流や、患者会などのサポートグループへの参加も、治療を続ける上で心強い支えとなるでしょう。
5. おわりに
肺胞蛋白症は、肺胞にサーファクタントが過剰に蓄積することで起こるまれな病気ですが、適切な診断と治療により、多くの患者さんが症状の改善を経験しています。
息切れや乾いた咳といった症状が現れる一方で、初期は無症状のことも多いため、早期発見・治療が重要です。
肺胞蛋白症に向き合うには、医療者やご家族、同じ病気を持つ方々との支え合いが大切です。ご不安なことやわからないことがあれば、医師や医療スタッフに相談しましょう。
息切れや咳など当てはまる症状が続く場合には、早めに呼吸内科をはじめとする医療機関を受診しましょう。
当院で、CTなどで肺胞蛋白症が疑われる患者さんは、速やかに高次医療機関へご紹介いたします。



